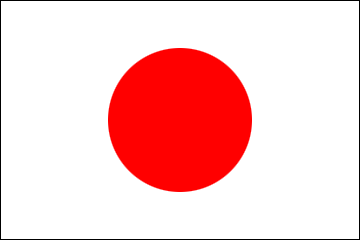堀内大使によるアフリカ情勢報告(第4回:2021年7月12日)
令和3年7月27日
アフリカ連合(AU)日本政府代表部の大使の堀内俊彦です。
Un homme qui lit en vaut deux. フランスにいる時に目にしたフレーズで、訳すと「読書する人は2人力」といった意味で、なるほどなと思いました。また、5月に休暇でしばらく日本に帰ったのですが、本屋で服部正也『ルワンダ中央銀行総裁日記』中公新書が平積みされていたのも印象的でした(この本は、ある方からODAに携わる者は必読と言われ以前読んで鮮烈な印象がありました)。
コロナ禍で今年の夏は(も)遠出をするかわりに読書と考えている方もいらっしゃると思います。そこでアフリカ関連のお勧めの本を頼まれてもいないのに勝手に挙げます。 私自身、今回赴任するに当たって、参考になりそうな本を探しましたが手探りでした。もしこれからアフリカに赴任する同僚に「面白そうな本ある?」と聞かれたらとの想定で記します。
(敬称略、順不同)
●石川薫・小浜裕人 『「未解」のアフリカ』勁草書房、2018年
もし一冊だけ、あるいは、何から読めばいい、と聞かれたらこの本をお勧めします。
「『歴史と正義は勝った者が書く』という人類史を通じた冷徹な事実が、特にアフリカに対してアンフェアであったことへの理解を少しでも広げたい」と、はしがきにあるように、アフリカ側の視点から歴史と開発課題を述べています。
●宮本正興・松田素二編『新書アフリカ史 改訂新版』講談社現代新書、2018年
ある地域・国を理解するのに、歴史(特に近現代史)は必須かと思いますが、その観点からはこの本もお勧めです。
●川田順造編『アフリカ史』山川出版社、2009年
この本も歴史理解の点から参考になりますが、特に、編著者らによる座談会の部分が面白いです。本自体は2009年発行と少し古いですが、座談会で述べられている問題意識は今でも十分妥当性があります。
●白戸圭一『アフリカを見る アフリカから見る』ちくま新書、2019年
ここ最近のアフリカの全体像を把握するのに参考になります。なお、本の帯には「それ、いつの時代のアフリカ観?」とありました。
●別府正一郎『アフリカ 人類の未来を握る大陸』集英社新書、2021年
これも最近のアフリカの全体像を把握するのに参考になります。現場での取材に基づいています。
●平野克己『経済大陸アフリカ』中公新書、2013年
2013年発行と少し古いのですが、日本は日本自身のためにもアフリカのダイナミズムを取り込むべきという視点が、読んだ当時新鮮でした。新著が待たれます。
●小川さやか『「その日暮らし」の人類学』光文社新書、2016年
副題に「もう一つの資本主義経済」とあるように、我々がこうでなければと信じているのとは違うやり方で経済を回すタンザニア商人の姿が描かれています。オルタナティブのヒントがあります。
なお、この本は、アフリカをフィールドにする研究者の研究論文ではない一般向けの本が面白い良い例でもありますが、同じように研究者が真面目に研究して真面目に書いているのに面白くなってしまった本として、青山潤『アフリカにょろり旅』講談社文庫、前野ウルド浩太郎『バッタを倒しにアフリカへ』光文社新書、などもあります。
●峯陽一『2100年の世界地図』岩波新書、2019年
人口動態の予測に基づき、2100年の世界がアジアとアフリカの時代(アフラシアの時代)になると説いています。人口動態にご関心ある方は、ポール・モーランド著 渡会圭子訳『人口で語る世界史』文藝春秋も面白いです。
●伊藤邦武編『世界哲学史8 現代」ちくま新書、2020年
アフリカの哲学について一章が充てられています。「アフリカ哲学は、西洋的枠組みを相対化する新しい概念枠を創造しつつある」とありました。ここでもオルタナティブへのヒントが語られています。
●川田順造編『アフリカ入門』新書館、1999年
少し古いのですが、放送大学のテキストをもとにした包括的な概説書で、一通りアフリカの基本について知るには良いと思います。
●ハンス・ロリングス他著 上杉周作、関美和訳『ファクトフルネス』日経BP、2019年
アフリカに特化した本ではありませんが、思い込み(バイアス)を排してデータをもとに世界を正しく捉えることを説いた本で、結果として、アフリカがますます重要になっていくことも訴えています。
●戸堂康之『開発経済学入門 第2版』新世社、2021年
(コロナ禍を受けて、そもそも「開発」とか「成長」も再定義が迫られていると思うのですが)アフリカを考える上で「開発」も避けて通れない問題です。改めて開発の問題に向き合おうと思った時に参考になります。「途上国経済が長期的に成長するためには、先進国の技術を吸収する力が最も重要」だそうです。
●伊藤亜聖『デジタル化する新興国』中公新書、2020年
デジタル化する世界の見取り図を、アフリカを含む新興国に焦点を当てて描いています。 アフリカから学びながら、そして、多くの方の声をお聞きしながら、取り組んで参ります。ご意見をお聞かせいただければ幸いです。
toshihiko.horiuchi@mofa.go.jp
2021年(令和3年)7月12日
アフリカ連合日本政府代表部 大使 堀内俊彦
Un homme qui lit en vaut deux. フランスにいる時に目にしたフレーズで、訳すと「読書する人は2人力」といった意味で、なるほどなと思いました。また、5月に休暇でしばらく日本に帰ったのですが、本屋で服部正也『ルワンダ中央銀行総裁日記』中公新書が平積みされていたのも印象的でした(この本は、ある方からODAに携わる者は必読と言われ以前読んで鮮烈な印象がありました)。
コロナ禍で今年の夏は(も)遠出をするかわりに読書と考えている方もいらっしゃると思います。そこでアフリカ関連のお勧めの本を頼まれてもいないのに勝手に挙げます。 私自身、今回赴任するに当たって、参考になりそうな本を探しましたが手探りでした。もしこれからアフリカに赴任する同僚に「面白そうな本ある?」と聞かれたらとの想定で記します。
(敬称略、順不同)
●石川薫・小浜裕人 『「未解」のアフリカ』勁草書房、2018年
もし一冊だけ、あるいは、何から読めばいい、と聞かれたらこの本をお勧めします。
「『歴史と正義は勝った者が書く』という人類史を通じた冷徹な事実が、特にアフリカに対してアンフェアであったことへの理解を少しでも広げたい」と、はしがきにあるように、アフリカ側の視点から歴史と開発課題を述べています。
●宮本正興・松田素二編『新書アフリカ史 改訂新版』講談社現代新書、2018年
ある地域・国を理解するのに、歴史(特に近現代史)は必須かと思いますが、その観点からはこの本もお勧めです。
●川田順造編『アフリカ史』山川出版社、2009年
この本も歴史理解の点から参考になりますが、特に、編著者らによる座談会の部分が面白いです。本自体は2009年発行と少し古いですが、座談会で述べられている問題意識は今でも十分妥当性があります。
●白戸圭一『アフリカを見る アフリカから見る』ちくま新書、2019年
ここ最近のアフリカの全体像を把握するのに参考になります。なお、本の帯には「それ、いつの時代のアフリカ観?」とありました。
●別府正一郎『アフリカ 人類の未来を握る大陸』集英社新書、2021年
これも最近のアフリカの全体像を把握するのに参考になります。現場での取材に基づいています。
●平野克己『経済大陸アフリカ』中公新書、2013年
2013年発行と少し古いのですが、日本は日本自身のためにもアフリカのダイナミズムを取り込むべきという視点が、読んだ当時新鮮でした。新著が待たれます。
●小川さやか『「その日暮らし」の人類学』光文社新書、2016年
副題に「もう一つの資本主義経済」とあるように、我々がこうでなければと信じているのとは違うやり方で経済を回すタンザニア商人の姿が描かれています。オルタナティブのヒントがあります。
なお、この本は、アフリカをフィールドにする研究者の研究論文ではない一般向けの本が面白い良い例でもありますが、同じように研究者が真面目に研究して真面目に書いているのに面白くなってしまった本として、青山潤『アフリカにょろり旅』講談社文庫、前野ウルド浩太郎『バッタを倒しにアフリカへ』光文社新書、などもあります。
●峯陽一『2100年の世界地図』岩波新書、2019年
人口動態の予測に基づき、2100年の世界がアジアとアフリカの時代(アフラシアの時代)になると説いています。人口動態にご関心ある方は、ポール・モーランド著 渡会圭子訳『人口で語る世界史』文藝春秋も面白いです。
●伊藤邦武編『世界哲学史8 現代」ちくま新書、2020年
アフリカの哲学について一章が充てられています。「アフリカ哲学は、西洋的枠組みを相対化する新しい概念枠を創造しつつある」とありました。ここでもオルタナティブへのヒントが語られています。
●川田順造編『アフリカ入門』新書館、1999年
少し古いのですが、放送大学のテキストをもとにした包括的な概説書で、一通りアフリカの基本について知るには良いと思います。
●ハンス・ロリングス他著 上杉周作、関美和訳『ファクトフルネス』日経BP、2019年
アフリカに特化した本ではありませんが、思い込み(バイアス)を排してデータをもとに世界を正しく捉えることを説いた本で、結果として、アフリカがますます重要になっていくことも訴えています。
●戸堂康之『開発経済学入門 第2版』新世社、2021年
(コロナ禍を受けて、そもそも「開発」とか「成長」も再定義が迫られていると思うのですが)アフリカを考える上で「開発」も避けて通れない問題です。改めて開発の問題に向き合おうと思った時に参考になります。「途上国経済が長期的に成長するためには、先進国の技術を吸収する力が最も重要」だそうです。
●伊藤亜聖『デジタル化する新興国』中公新書、2020年
デジタル化する世界の見取り図を、アフリカを含む新興国に焦点を当てて描いています。 アフリカから学びながら、そして、多くの方の声をお聞きしながら、取り組んで参ります。ご意見をお聞かせいただければ幸いです。
toshihiko.horiuchi@mofa.go.jp
2021年(令和3年)7月12日
アフリカ連合日本政府代表部 大使 堀内俊彦