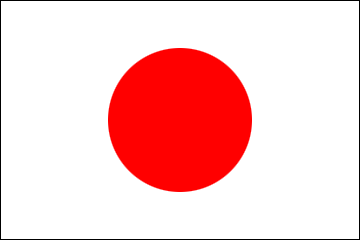堀内大使によるアフリカ情勢報告(第6回:2021年10月29日)
令和3年10月29日
アフリカ連合(AU)日本政府代表部の大使の堀内俊彦です。アフリカがどこに向かおうとしているのかをお伝えしようと思い、メルマガ(第6号)をお送りします。
9月にアフリカ大陸自由貿易圏(以下AfCFTA)事務局のトップのワムケレ・メネ(Wamkele Mene)事務局長にお会いしました。メネ事務局長は普段はAfCFTAの事務局のあるガーナの首都アクラにいるのですが、アフリカ連合(AU)の本部のあるエチオピアのアディスアベバまで出張で来られ、限られた滞在時間の中でのアポ先に日本も選んでくれました。
AfCFTAはその協定が2019年に発効し、2021年1月から実施に移されている、世界で最大級の貿易協定で、アフリカ域内での貿易を円滑にすることを目的としています(なお、市場統合の構想自体は既に1980年頃からありました)。アフリカは人口40億人の単一市場に向けての大きな一歩を踏み出しました(注:国連の中位推計では2100年の世界の人口は約100億人、そのうちアフリカが40億人)。
今回は、メネ事務局長との意見交換も参考に、AfCFTAの成果(期待される成果を含む)と今後の課題を3つずつ記したいと思います。
【成果】
●アフリカも自由貿易の旗手
とかく閉鎖的に内にこもりがちなアクターが多い中で、アフリカが自由で開放的な貿易を重視するとの姿勢、価値観を示した意義は大変大きいと思います。
●域内経済活動の活性化
アフリカの経済の課題の一つは、域内貿易が低調なことです(例えばヨーロッパの総輸出額に占める域内貿易は約69%なのに対し、アジアは約60%、アフリカは約16%(UNCTAD))。AfCFTAには、まずはアフリカ域内の貿易を活発にすることが一番に期待されています。私が意見交換したあるヨーロッパの有力国の大使も「アフリカのある1ヶ国に拠点を置いて、そこからアフリカ全体に向けてビジネスが出来ることは大きな魅力」と言っていました。AfCFTAには後述するような課題もあり、その実効性に懐疑的な見方もあります。しかしながら、この大使の発言のようにAfCFTAを積極的に活用しようとの機運が生まれているのも事実です。メネ事務局長も、中小企業や若者の起業家をはじめアフリカの民間セクターの多くがAfCFTAによる市場の拡大という恩恵を受けるだろうと語っていました。
●人為的な国境を克服しようとの試み
アフリカの国々の国境は、その多くが植民地分割の際に人為的に引かれたものです。しかしながら、アフリカの国々は、AUの前身であるOAU(アフリカ統一機構)が1963年にできた時に、国境線の見直しには手をつけないことに決めました。植民地支配の際に押し付けられた国境ではあるものの、国境をいじることはパンドラの箱を開けることになるがゆえの苦渋の決断でした。今回のAfCFTAは、その人為的な国境を少なくとも経済の面では超克しようとの試みと言えます。統合は実利的な分野から進めるのが正攻法だと思います。AfCFTAが今後どうなっていくかは、アフリカ統合の今後を占う大きな指標になります。
【課題】
●要塞化?
AfCFTAが、(アフリカ域内の貿易は活発にするものの)アフリカの域外に対しては要塞化するのではとの危惧の声も当地の外交団からは聞きます。これに対するAfCFTA側の見解は、AfCFTAはアフリカ域内だけでなく、日本を含むアフリカ域外の国にとっても必ずや益になるというものです。AfCFTAがアフリカ域内だけでなくアフリカ域外に対しても開放性を持つかどうかについては、注意を払いたいと思います。
●まだ続く交渉
AfCFTAの実効性に懐疑的な見方の根拠の一つが、重要論点を含めまだまだ交渉中、あるいは交渉が残っているという点です。フェーズ1(物品貿易とサービス貿易)の積み残しの論点である原産地規則、譲許表や、フェーズ2で予定される知的財産権、投資章、競争政策の交渉、フェーズ3で予定されるEコマースの交渉などです。なお、この点については、メネ局長は、まずは目の前のフェーズ1の残りの課題を優先させたいとのことでした。優先順位の高い項目から目に見える具体的成果を挙げることが今後の交渉にも好影響を与えるとの考えかと思われます。
アフリカと一口で言っても、国によって産業構造も貿易構造も大きく異なるので、AfCFTAに対する向き合い方も一様ではありません。引き続き交渉を注視していきたいと思います。
●何を、どうやって実際に流通させるのか
当地で多くのAU関係者や外交団がAfCFTAの実施面での課題として挙げているのが、実際の物流や取引を支える税関等の制度的インフラ、道路・鉄道等の物理的インフラをどうするかということ、そして貿易を含むあらゆる経済社会活動の前提となる平和と安定の問題です。また、流通させる生産物、製品をどう生み出すか、つまり産業をどう育成するかという点です。これらの点についても、メネ事務局長からは日本の民間セタクー、政府への熱い期待が表明されました。
自由貿易で痛みを被る人やセクターをどう手当てするかとの以前からの課題に加え、貿易も「グリーン」でなければいけないとの新たなエコロジー上の要請、貿易の効用を高めまた円滑にするDXという挑戦、新型コロナ感染症で顕在化したバリューチェーンの見直しや主権主義(自前主義)への回帰などの課題をはじめ、AfCFTAにも難しい舵取りが迫られます。まさに、ノーベル賞を取ったBanerjeeとDufloの本のタイトルを借りるなら『Good Economics for Hard Times』が求められています。
ただ見方を変えれば、これはまさに、日本とアフリカが一緒になってより良い国際的な経済秩序、ルールを作っていくという、今後ありうべき日本・アフリカ関係の協同の象徴にもなり得ると感じています。
アフリカの在来知からも学びながら、そして、多くの方の声をお聞きしながら、取り組んで参ります。ご意見をお聞かせいただければ幸いです。
2021年(令和3年)10月29日
アフリカ連合日本政府代表部 大使
堀内俊彦
9月にアフリカ大陸自由貿易圏(以下AfCFTA)事務局のトップのワムケレ・メネ(Wamkele Mene)事務局長にお会いしました。メネ事務局長は普段はAfCFTAの事務局のあるガーナの首都アクラにいるのですが、アフリカ連合(AU)の本部のあるエチオピアのアディスアベバまで出張で来られ、限られた滞在時間の中でのアポ先に日本も選んでくれました。
AfCFTAはその協定が2019年に発効し、2021年1月から実施に移されている、世界で最大級の貿易協定で、アフリカ域内での貿易を円滑にすることを目的としています(なお、市場統合の構想自体は既に1980年頃からありました)。アフリカは人口40億人の単一市場に向けての大きな一歩を踏み出しました(注:国連の中位推計では2100年の世界の人口は約100億人、そのうちアフリカが40億人)。
今回は、メネ事務局長との意見交換も参考に、AfCFTAの成果(期待される成果を含む)と今後の課題を3つずつ記したいと思います。
【成果】
●アフリカも自由貿易の旗手
とかく閉鎖的に内にこもりがちなアクターが多い中で、アフリカが自由で開放的な貿易を重視するとの姿勢、価値観を示した意義は大変大きいと思います。
●域内経済活動の活性化
アフリカの経済の課題の一つは、域内貿易が低調なことです(例えばヨーロッパの総輸出額に占める域内貿易は約69%なのに対し、アジアは約60%、アフリカは約16%(UNCTAD))。AfCFTAには、まずはアフリカ域内の貿易を活発にすることが一番に期待されています。私が意見交換したあるヨーロッパの有力国の大使も「アフリカのある1ヶ国に拠点を置いて、そこからアフリカ全体に向けてビジネスが出来ることは大きな魅力」と言っていました。AfCFTAには後述するような課題もあり、その実効性に懐疑的な見方もあります。しかしながら、この大使の発言のようにAfCFTAを積極的に活用しようとの機運が生まれているのも事実です。メネ事務局長も、中小企業や若者の起業家をはじめアフリカの民間セクターの多くがAfCFTAによる市場の拡大という恩恵を受けるだろうと語っていました。
●人為的な国境を克服しようとの試み
アフリカの国々の国境は、その多くが植民地分割の際に人為的に引かれたものです。しかしながら、アフリカの国々は、AUの前身であるOAU(アフリカ統一機構)が1963年にできた時に、国境線の見直しには手をつけないことに決めました。植民地支配の際に押し付けられた国境ではあるものの、国境をいじることはパンドラの箱を開けることになるがゆえの苦渋の決断でした。今回のAfCFTAは、その人為的な国境を少なくとも経済の面では超克しようとの試みと言えます。統合は実利的な分野から進めるのが正攻法だと思います。AfCFTAが今後どうなっていくかは、アフリカ統合の今後を占う大きな指標になります。
【課題】
●要塞化?
AfCFTAが、(アフリカ域内の貿易は活発にするものの)アフリカの域外に対しては要塞化するのではとの危惧の声も当地の外交団からは聞きます。これに対するAfCFTA側の見解は、AfCFTAはアフリカ域内だけでなく、日本を含むアフリカ域外の国にとっても必ずや益になるというものです。AfCFTAがアフリカ域内だけでなくアフリカ域外に対しても開放性を持つかどうかについては、注意を払いたいと思います。
●まだ続く交渉
AfCFTAの実効性に懐疑的な見方の根拠の一つが、重要論点を含めまだまだ交渉中、あるいは交渉が残っているという点です。フェーズ1(物品貿易とサービス貿易)の積み残しの論点である原産地規則、譲許表や、フェーズ2で予定される知的財産権、投資章、競争政策の交渉、フェーズ3で予定されるEコマースの交渉などです。なお、この点については、メネ局長は、まずは目の前のフェーズ1の残りの課題を優先させたいとのことでした。優先順位の高い項目から目に見える具体的成果を挙げることが今後の交渉にも好影響を与えるとの考えかと思われます。
アフリカと一口で言っても、国によって産業構造も貿易構造も大きく異なるので、AfCFTAに対する向き合い方も一様ではありません。引き続き交渉を注視していきたいと思います。
●何を、どうやって実際に流通させるのか
当地で多くのAU関係者や外交団がAfCFTAの実施面での課題として挙げているのが、実際の物流や取引を支える税関等の制度的インフラ、道路・鉄道等の物理的インフラをどうするかということ、そして貿易を含むあらゆる経済社会活動の前提となる平和と安定の問題です。また、流通させる生産物、製品をどう生み出すか、つまり産業をどう育成するかという点です。これらの点についても、メネ事務局長からは日本の民間セタクー、政府への熱い期待が表明されました。
自由貿易で痛みを被る人やセクターをどう手当てするかとの以前からの課題に加え、貿易も「グリーン」でなければいけないとの新たなエコロジー上の要請、貿易の効用を高めまた円滑にするDXという挑戦、新型コロナ感染症で顕在化したバリューチェーンの見直しや主権主義(自前主義)への回帰などの課題をはじめ、AfCFTAにも難しい舵取りが迫られます。まさに、ノーベル賞を取ったBanerjeeとDufloの本のタイトルを借りるなら『Good Economics for Hard Times』が求められています。
ただ見方を変えれば、これはまさに、日本とアフリカが一緒になってより良い国際的な経済秩序、ルールを作っていくという、今後ありうべき日本・アフリカ関係の協同の象徴にもなり得ると感じています。
アフリカの在来知からも学びながら、そして、多くの方の声をお聞きしながら、取り組んで参ります。ご意見をお聞かせいただければ幸いです。
2021年(令和3年)10月29日
アフリカ連合日本政府代表部 大使
堀内俊彦