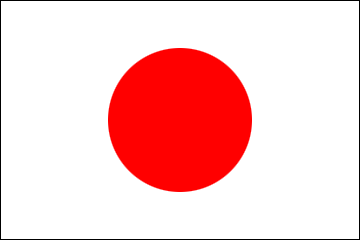堀内大使によるアフリカ情勢報告(第13回:2022年12月2日)
令和4年12月2日
アフリカ連合(AU)日本政府代表部(AU代表部)の大使の堀内俊彦です。メルマガ(第13号)をお送りします。
私がいるAU代表部の任務の一つとして学術・知的交流分野での日本とアフリカの関係強化があります。その実践として毎年、当地(エチオピアの首都のアディスアベバ)のシンクタンクのIPSS(平和安全保障研究所)とセミナーを共催しています(IPSSは、アジスアベバ大学附属の高等学術機関でもあります)。
今回は、11月24日に開いたそのセミナー「アフリカの平和と安全保障とTICAD8(筆者注:今年8月にチュニジアで開催した第8回アフリカ開発会議)」についてご紹介します(少しPRをさせてください)。
なお、学術交流に関しては、日本の経験をアフリカと共有するJICA(国際平和協力機構)による連続講座「JICAチェア」もありますが、これについてはまた別の機会にご紹介したいと思います。
【紛争の姿形は変わっても課題であり続ける平和と安全保障】
植民地解放闘争から、権力や利権を巡っての内戦へ、そして農村部を根拠として跋扈するジハーディストとの戦いへというように、紛争の主体や態様は変遷してきていますが、平和と安全保障は常にアフリカにとって大きな課題です。今回のセミナーでは、アフリカ自身の安全保障分野での取り組みとそれに呼応する形での日本の関与のあり方について有識者を招いて議論していただきました。日本からはパネリストとして、政策研究大学院大学(GRIPS)の上江洲佐代子さんにもオンラインでご参加いただきました。
【聴衆のコメントに見るアフリカ側の関心】
セミナーでは聴取からも多くの質問やコメントが出されました。いくつかご紹介します。
・テロの根本的原因や資金源の問題の重要性
・アフリカの多くの取り組みが、制度面が先行して予算的手当てや実行(実効)が伴わない問題
・若者重視の必要性(聴衆にも学生が多く勇気づけられました。なお、AUも若者を平和の担い手として重視しています)
・AUのモットーでもある「African solutions to African problems」を実践する際の日本を含む外部アクターの役割
・伝統的な指導者の活用などアフリカ固有の解決策の活用
これらのコメントをどう日本の政策に反映するか課題を頂戴した気持ちです。
【フランス語圏への配慮も】
なお、日頃からフランス語圏出身者の方とお付き合いしていると、英語(圏)の優位に対する不満をよく聞かされるので、私も冒頭挨拶は英語で、閉会挨拶はフランス語で行いました。この点もアフリカで何かやる時の留意事項です(なお、AUの公用語はアラビア語、英語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語、スワヒリ語、アフリカの諸言語です)。
【同じ部屋に】
一つのセミナーだけをとっても、対立する考えを含めて様々な意見が出されます。まずは「同じ部屋」に集まることが大事だと実感しました(もちろん、ロシアのウクライナ侵攻に対してのように毅然とした態度を表明しなければいけない場合もありますが)。そのような場(知的プラットフォーム)を作って提供できるのも日本の強みですし責務だと思います。
多くの方の様々な声をお聴きしながら、アフリカについて考え、行動していきたいと思います。ご意見頂戴できましたら幸いです。
2022年(令和4年)12月2日
アフリカ連合日本政府代表部 大使
堀内俊彦
私がいるAU代表部の任務の一つとして学術・知的交流分野での日本とアフリカの関係強化があります。その実践として毎年、当地(エチオピアの首都のアディスアベバ)のシンクタンクのIPSS(平和安全保障研究所)とセミナーを共催しています(IPSSは、アジスアベバ大学附属の高等学術機関でもあります)。
今回は、11月24日に開いたそのセミナー「アフリカの平和と安全保障とTICAD8(筆者注:今年8月にチュニジアで開催した第8回アフリカ開発会議)」についてご紹介します(少しPRをさせてください)。
なお、学術交流に関しては、日本の経験をアフリカと共有するJICA(国際平和協力機構)による連続講座「JICAチェア」もありますが、これについてはまた別の機会にご紹介したいと思います。
【紛争の姿形は変わっても課題であり続ける平和と安全保障】
植民地解放闘争から、権力や利権を巡っての内戦へ、そして農村部を根拠として跋扈するジハーディストとの戦いへというように、紛争の主体や態様は変遷してきていますが、平和と安全保障は常にアフリカにとって大きな課題です。今回のセミナーでは、アフリカ自身の安全保障分野での取り組みとそれに呼応する形での日本の関与のあり方について有識者を招いて議論していただきました。日本からはパネリストとして、政策研究大学院大学(GRIPS)の上江洲佐代子さんにもオンラインでご参加いただきました。
【聴衆のコメントに見るアフリカ側の関心】
セミナーでは聴取からも多くの質問やコメントが出されました。いくつかご紹介します。
・テロの根本的原因や資金源の問題の重要性
・アフリカの多くの取り組みが、制度面が先行して予算的手当てや実行(実効)が伴わない問題
・若者重視の必要性(聴衆にも学生が多く勇気づけられました。なお、AUも若者を平和の担い手として重視しています)
・AUのモットーでもある「African solutions to African problems」を実践する際の日本を含む外部アクターの役割
・伝統的な指導者の活用などアフリカ固有の解決策の活用
これらのコメントをどう日本の政策に反映するか課題を頂戴した気持ちです。
【フランス語圏への配慮も】
なお、日頃からフランス語圏出身者の方とお付き合いしていると、英語(圏)の優位に対する不満をよく聞かされるので、私も冒頭挨拶は英語で、閉会挨拶はフランス語で行いました。この点もアフリカで何かやる時の留意事項です(なお、AUの公用語はアラビア語、英語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語、スワヒリ語、アフリカの諸言語です)。
【同じ部屋に】
一つのセミナーだけをとっても、対立する考えを含めて様々な意見が出されます。まずは「同じ部屋」に集まることが大事だと実感しました(もちろん、ロシアのウクライナ侵攻に対してのように毅然とした態度を表明しなければいけない場合もありますが)。そのような場(知的プラットフォーム)を作って提供できるのも日本の強みですし責務だと思います。
多くの方の様々な声をお聴きしながら、アフリカについて考え、行動していきたいと思います。ご意見頂戴できましたら幸いです。
2022年(令和4年)12月2日
アフリカ連合日本政府代表部 大使
堀内俊彦